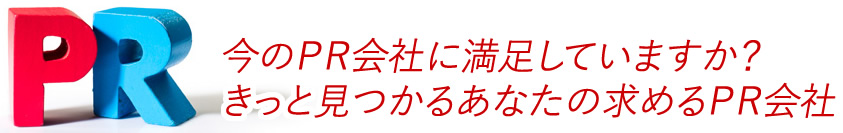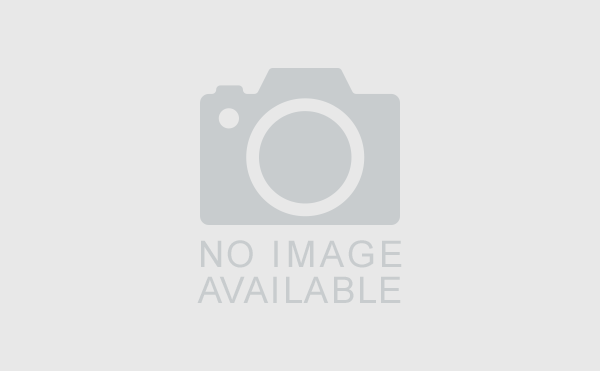広報・PRで受賞・表彰のプレスリリースを作成する際のポイント5選
広報・PRで受賞・表彰のプレスリリースを作成する際のポイント5選
この記事では広報・PR担当者の皆さんに向けて、受賞・表彰に関するプレスリリースの作成・配信のポイントなどについてお伝えしていきます。
特に「受賞・表彰しそうな商品・サービスがあるもののどう広報・PRすればいいかわからない」という方におすすめの内容となっています。
本記事では受賞・表彰についてのプレスリリースの作成・配信するメリット、作成や配信に関するポイント、注意点、さらにプレスリリースを出さない場合の対応方法や、自社社員への周知などについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
広報・PRで受賞・表彰に関するプレスリリースを作成・配信するメリット3選
それでは受賞・表彰に関するプレスリリースを作成・配信することの主なメリットを3つ紹介しますので、広報・PR担当者の皆さんはぜひ参考にしてください。
メリット①:受賞・表彰の事実を広くアピールできる
当たり前ですがプレスリリースを作成・配信することで受賞・表彰の事実をより広くアピールできます。受賞・表彰の種類や規模によっては目立たないので、プレスリリースの作成・配信によって広報・PR効果を底上げするのは重要なことといえます。
メリット②:その分野で高く評価されていることをアピールできる
基本的に受賞・表彰は、対象の商品・サービス・技術・人材などが、その分野で高く評価されていることの裏付けとなります。そのためプレスリリースを作成・配信して広くアピールしないのはもったいないといえます。
メリット③:改めて商品・サービスをアピールできる
受賞・表彰のプレスリリースを作成・配信することで、改めて商品・サービスをアピールすることができます。特に「受賞・表彰の理由になったポイント」を目立たせることで、新たな顧客を獲得したり、既存の顧客からの信頼を高めたりすることができるかもしれません。
受賞・表彰に関するプレスリリースに入れるべきポイント5つ
続いては受賞・表彰に関するプレスリリースに入れるべきポイントをいくつか紹介していきます。商品やサービスのプレスリリースとは違う部分もあるので、広報・PR担当者の皆さんはぜひ参考にしてください。
ポイント①:賞の正式名称など基本情報を明記する
賞の基本情報を明記しましょう。具体的には正式名称、受賞や表彰の詳細、主催団体・会社の基本情報、主催団体・会社のサイトのURLなどです。
正式名称などを書かないとプレスリリースを読んだメディア関係者は、賞などの情報にたどり着けない可能性があるので気を付けてください。また、似た名前の違う賞と誤認されてしまう恐れもあります。
ポイント②:認定ロゴマークがあれば載せる
受賞・表彰に際して認定ロゴマークが付与されるケースもあります。該当する場合はプレスリリースに「これが認定ロゴマークです」とわかるようなテキストと一緒に載せましょう。
ただ、認定ロゴマークの使い方についてルールが設けられているケースもあるのでしっかりと確認してからにしてください。
ポイント③:受賞・表彰された商品やサービス、技術や人物の紹介
プレスリリースで受賞・表彰された商品やサービス、技術や人物の紹介をしましょう。基本情報はもちろん書きますが、それだけでなく「受賞・表彰の理由になったセールスポイント」もできるだけ詳しく記載しましょう。
ただし商品やサービス、技術や人物について全く知らない人でも理解できるように、わかりやすい表現を使い、過不足なく説明することが大事です。
ポイント④:受賞・表彰された商品・サービスの関係者、受賞人物本人のコメントを載せる
プレスリリースには受賞・表彰された商品・サービスの関係者や、受賞人物本人のコメントを載せましょう。これによって「単なる報告」ではなく、「共感や感動を呼ぶプレスリリース」にすることができますし、理念などに共感した人が新しくファンになって、企業を後押ししてくれる可能性もあります。コメントに入れるべき要素は主に以下の通りです。
- 商品やサービスを開発した理由
- 開発にするにあたっての困難
- その困難をどう乗り越えたか
- 商品やサービスの強みだと感じている部分
- 今後の展望(改良していく、品質維持に努めるなど)
特に「困難を乗り越えたエピソード」は共感を呼ぶために重要なので必ず入れましょう。「成功続きでした」というだけでは人の心には響きにくいです。そのため「実はあまり苦労しなかった」という場合でも、「どこに力を入れたか」などをきちんと載せることが大事です。
ポイント⑤:受賞式・表彰式があればその写真や動画を載せる
受賞式・表彰式があればその写真や動画をプレスリリースに載せることをおすすめします。具体的には会場の様子、受賞・表彰の瞬間、記念品の写真、記念撮影の様子などの写真・動画を載せるといいでしょう。
ただ、受賞式・表彰式の様子までプレスリリースに載せる場合、「受賞・表彰の情報だけのプレスリリース」よりも作成・配信できるタイミングが遅くなる可能性が高いです。
そのためプレスリリースを可能な限り作成し、「あとは写真・動画を載せるだけ」にしておき、受賞式・表彰式が終わったらすぐにプレスリリースを完成させて、その後数日中に配信することをおすすめします。
受賞・表彰のプレスリリースの作成・配信に関する注意点3つ
続いては受賞・表彰のプレスリリースを作成・配信するにあたっての注意点をいくつか紹介していきます。「主催者」という存在がいるからこそ気を付けるべき部分もあるので、広報・PR担当者の皆さんはぜひ参考にしてください。
注意点①:プレスリリース配信のタイミングに気を付ける
プレスリリース配信のタイミングに気を付けてください。基本的には「主催者が受賞・表彰に関して発表する」→「受賞・表彰された側のプレスリリース配信などが解禁」という順番になっています。先に発表するとトラブルにつながりかねないので注意が必要です。
注意点②:ルールで決まっている場合はプレスリリース配信前に主催者のチェックを受ける
プレスリリースを配信する前に、主催者からのチェックを受けなければならないケースもあるので事前に確認を取っておきましょう。そして主催者が迅速にチェックしてくれるとは限らないので、早めに動き出すことが大事です。
急いでプレスリリースを配信したいかもしれませんが、主催者がいるからこそのことなので、敬意をもって丁寧に対応してください。
注意点③:受賞に関連して行う取り組みについても記載する
受賞に関連してなんらかの取り組み(キャンペーンなど)をする場合は、それについても記載しましょう。「受賞したこと」と「取り組み」について分割してプレスリリースを作成・配信したくなるかもしれませんが、分けると「取り組み」への注目度が下がりやすいのでおすすめしません。
さらにキャンペーンなどの詳細情報を書いたウェブページも作っておき、そこにアクセスできるURLをプレスリリースに載せておくといいでしょう。
こういった施策をするためには広報・PR担当者が、「取り組み」についても早めに情報を掴んでまとめておく必要があります。そのため関係部署としっかり連携して事を進めることが大事といえます。
プレスリリースを出さない場合も広報・PR担当者がアピールする
なんらかの理由で受賞・表彰に関するプレスリリースを出さない場合でも、広報・PR担当者ができる範囲のアピールをすることをおすすめします。例えば以下の方法があります。
- 企業公式サイトに基本情報を載せる
- SNSの投稿でアピール
- メールマガジンでアピール
いずれにしても受賞・表彰について全く触れないのはもったいないですし、ほとんど誰も気付いてくれない可能性もあります。
自社社員にも受賞・表彰について周知する
また、受賞・表彰について社員にも周知しましょう(広報・PR担当者が主導する)。たとえある程度権威のある受賞・表彰だったとしても興味がない社員は「自分には関係がない」と感じるかもしれないからです。
ですが受賞・表彰に関して社員が知れば、受賞・表彰された本人も他の社員も満たされた気持ちになり、モチベーションが上がることでしょう。
まとめ
受賞・表彰についてアピールしないと意外とそのまま埋もれやすいので、プレスリリースの作成・配信などをして広報・PR担当者が積極的に主張していくことをおすすめします。
ただ、賞の主催者側でルールを決めていることもあるので、プレスリリースの記載内容や配信タイミングには気を付けてください。また、なんらかの理由でプレスリリースの作成・配信をしないとしても、他の方法で最低限のアピールはしましょう。
The post 広報・PRで受賞・表彰のプレスリリースを作成する際のポイント5選 first appeared on PR会社ならプレスリリースと広報戦略のフロンティアコンサルティング.
Source: PR最新情報